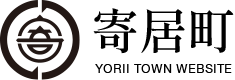本文
中東呼吸器症候群(MERS)について
5月11日に韓国において発生したMERS(中東呼吸器症候群)については、医療従事者のほか、同じ病棟での接触患者、その家族への二次感染が多発しており、三次感染も発生しています。死者も増え続けています。
現在まで、日本国内での発生は確認されておりません。必要以上に不安がることはありませんが、適切な行動を心がけましょう。
中東呼吸器症候群(MERS)とは
中東呼呼吸器症候群(MERS)は、平成24年に初めて患者が報告された新しい種類のコロナウイルスによる感染症です。
日本における呼称は、病原体名「MERS(マーズ)コロナウイルス」、感染症名「中東呼吸器症候群(MERS)」とされています。厚生労働省は、この疾病を感染症法上の二類感染症に指定しています。
中東地域に居住または渡航歴のある者、あるいはMERS患者との接触歴のある者からの患者発生が継続的に報告されています。
発生地域
主に、中東地域(アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン、レバノン)で患者が報告されています。
このほか、ヨーロッパ(イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、ドイツ、フランス、トルコ)やアフリカ(アルジェリア、エジプト、チュニジア)、アジア(フィリピン、マレーシア、韓国)及び北米大陸(アメリカ合衆国)でも患者は報告されていますが、これらはすべて中東地域で感染した人(輸入症例)もしくはその輸入症例患者と接触した人であることがわかっています。
病原体と感染経路
病源体は、コロナウイルス(MERS-CoV)です。
平成15年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因病原体であるSARSコロナウイルスとは近縁ですが、異なる種類のウイルスです。
感染経路は、正確には分かっていませんが、ヒトコブラクダが感染源の一つであると推定されています。ラクダとの濃厚接触や未殺菌のラクダ乳の摂取などの危険性が指摘されています。
その一方で、患者の中には動物との接触歴がない人も多く含まれており、家族間、医療機関における患者間、患者-医療従事者間など、濃厚接触者間での限定的な「ヒトからヒト」への感染も一部報告されています。
症状
主な症状は、発熱、咳、息切れや呼吸困難を伴う急性呼吸器症状です。
また、嘔吐、下痢などの消化器症状を伴う場合もあります。
潜伏期間は、2日から14日(平均5日程度)と言われており、特に高齢の方や糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人は重症化する傾向があります。
治療
特別な治療法は無く、予防接種もありません。症状に応じた対症療法が行われます。
渡航する方の注意点
旅行前
・糖尿病や慢性肺疾患、免疫不全などの持病(基礎疾患)がある方は、MERSに限らず、一般的に感染症にかかりやすいので、旅行の前にかかりつけの医師に相談し、渡航の是非について検討してください。
・渡航前に現地の最新の情報を検疫所ホームページ、外務省 海外安全ホームページ、在サウジアラビア日本国大使館ホームページなどで確認してください。
旅行中
・現地では、こまめに手を洗う、加熱が不十分な食品(未殺菌の乳や生肉など)や不衛生な状況で調理された料理をさけ、果物、野菜は食べる前によく洗う、といった一般的な衛生対策を心がけてください。
・咳やくしゃみの症状がある人や、動物(ラクダを含む)との接触は可能な限り避けましょう。
・咳、発熱などの症状がある場合は、他者との接触を最小限にするとともに、咳エチケット(1 マスクをする、2 咳・くしゃみの際はティッシュペーパーなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむける、3 使用したティッシュペーパーはごみ箱に捨て、手を洗うなど)を実行しましょう。日常生活に支障が出る程の症状がある場合は、医療機関を受診してください。
旅行後
・帰国時に発熱や咳などの症状がある方は、空港内等の検疫所へご相談ください。
・MERS患者が発生している地域から帰国後14日以内に、発熱や咳などの症状がみられた場合には、医療機関を受診する前に、事前に最寄りの保健所に御相談ください。
・症状がある間は、他者との接触を最小限にするとともに、咳エチケットを実行してください。
参考
- MERSについて(厚生労働省)<外部リンク>
- 海外で健康に過ごすために(厚生労働省検疫所)<外部リンク>