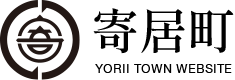本文
高額療養費制度について
高額療養費制度とは
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請で認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
また、マイナ保険証を利用するか、あらかじめ国民健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。ただし、複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの請求があります。また、同一の医療機関でも、入院と外来を受診した場合はそれぞれ別に計算されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(入院・外来ごと、医科・歯科ごと)で自己負担額が21,000円を超えたものが高額療養費の合算対象となります。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| イ | 所得600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
所得210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
70歳以上の方は、自己負担額の多少にかかわらず、すべてが合算対象となります。その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分 | 外来の自己負担限度額 (個人ごと) |
外来+入院の自己負担限度額 (世帯ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% <4回目以降140,100円> |
|
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% <4回目以降93,000円> |
|
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% <4回目以降44,400円> |
|
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <4回目以降44,000円> |
| 低所得者2 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 (住民税非課税世帯) |
15,000円 | |
申請の方法について
医療機関からの診療報酬明細書に基づき、診療月の3か月後に支給申請書を郵送します。必要事項をご記入いただき、申請期限までに町民課窓口または郵送にて申請してください。申請期限を過ぎての申請は、申請月の翌月以降の支給となります。
なお、診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、支給申請書に同封しているお知らせをご確認ください。
限度額適用認定証の申請について
申請に必要なもの
※国民健康保険税を滞納している世帯の70歳未満の方には、限度額適用認定証が交付できない場合があります。
申請書の様式
限度額適用・標準負担額認定申請書 [PDFファイル/51KB]
有効期限について
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日となっております。有効期限経過後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請が必要になります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の申請は不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※国民健康保険税を滞納している世帯の70歳未満の方は、マイナ保険証を利用しても限度額の適用ができない場合があります。
高額療養費の申請簡素化について
これまで、国民健康保険において高額療養費が発生した場合、町より国民健康保険高額療養費支給申請書を送付し、世帯主による申請が必要でした。
令和4年4月診療分より「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出すると、次回以降の国民健康保険高額療養費支給申請書の提出が不要となります。
申請の方法について
令和4年4月以降、高額療養費に該当した場合、初回時のみ「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を送付します。必要事項をご記入いただき、町民課窓口または郵送にて申請してください。
※診療月の翌月1日から2年で時効となる点に変更はありません。
簡素化が停止となる場合
次のような場合は、申請手続の簡素化を停止し、これまでと同様に該当月ごとの申請が必要となります。
・世帯主が死亡した場合
・死亡その他の事由により振込ができなくなった場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
・申請書の内容に偽りその他不正があった場合
・その他町長が認めた場合
注意事項
簡素化適用(翌月)以降「国民健康保険高額療養費支給申請のお知らせ」は送付されません。
支給金額や振込日等は通知される「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」をご確認ください。
後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります。