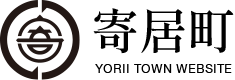本文
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療にかかる費用(医療機関などで支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費(国、県、市町村)が充てられています。また、約4割は現役世代の支援金でまかなわれ、残りの約1割を保険料として被保険者全員に納めていただくことになります。保険料は大切な財源であり、保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合の条例に基づき、埼玉県後期高齢者医療広域連合が賦課を行います。なお、後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料(年額)=均等割額+所得割額
| 均等割額 | 45,930円 |
| 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×所得割率9.03% |
| 賦課限度額(年間上限額) | 80万円 |
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
(雑損失の繰越控除額は控除しません。)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。また、令和2年度以前は、合計所得金額によらず「基礎控除額33万円」となります。 - 年金収入のみの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されません。
- 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り、軽減された所得割率(8.42%)が適用されます。
- 令和5年度末までに既に後期高齢者医療保険の被保険者である方及び令和6年度中に障がい認定により加入される方は、令和6年度に限り、賦課限度額は73万円となります(令和7年度は、80万円となります)。
保険料の軽減
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減判定基準以下の場合には、均等割額を7割、5割、2割軽減します。
| 軽減割合 | 軽減判定基準(年金・給与所得者の数は2人以上いる場合に計算します) | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数−1) | 13,700円/年 |
| 5割 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数−1) | 22,960円/年 |
| 2割 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数−1) | 36,740円/年 |
- 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。 なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額で軽減判定の所得を計算します。
- 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
- 軽減判定は4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
- 実際の保険料は所得割額との合算となります。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、協会けんぽや健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者であった方の保険料額は、加入した日の属する月から2年を経過する月まで軽減されます。
均等割額・・・5割軽減
所得割額・・・0円(負担なし)
- 市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外です。
- 被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、割合の多い軽減措置が適用されます。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの差引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。原則特別徴収による納付となりますが、特別徴収の適用基準を外れた場合、またはご加入後一定期間は普通徴収となりますので、ご注意ください。
特別徴収
年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が差し引きされます。
毎年10月が特別徴収開始月となり、対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。
4・6・8月は保険料決定前の仮徴収といい、2月に特別徴収を行った人のみ、同額で差し引きします。
10・12・翌年2月は保険料決定後の本徴収であり、年間の保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けた額を差し引きします。
次のすべてに該当する方が対象です。
- 年金額が年18万円(受給する複数の年金の合計額ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額)以上の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 1回(期)当たりの介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金の1回当たりの受給額の1/2以下の方
普通徴収
毎年7月に埼玉県後期高齢者広域連合にて保険料(年額)が賦課されます。(年度の途中において被保険者資格を取得された方は資格取得月の翌月に賦課されます。)
普通徴収は7月から翌年2月までの8回(期)に分けて口座振替または納付書により納めていただき、毎月末が納期限となります。(ただし、12月は12月25日納期限。また、月末が祝祭休日の場合は翌月初が納期限)
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 特別徴収の対象とならない方
- 口座振替の申し込みを行い、特別徴収から普通徴収への納付方法変更の申し出をされた方
- 被保険者資格を取得した後、一定期間が経過するまでの方
- 市町村が変わる引越しや保険料の減額等により特別徴収が中止となった方
- 特別徴収の方で、保険料が年度途中で増額となった方(特別徴収と普通徴収で納めていただきます)
口座振替
指定金融機関の窓口にて申し込みいただくことで、納期限に保険料を振替えます。一度口座を登録すれば、普通徴収から特別徴収、特別徴収から普通徴収に切り替わったときも更新の手続きは必要ありません。また、保険料の変更等により還付金が発生した場合も口座振替の登録口座へ還付されます。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度は異なる医療保険です。このため、国民健康保険税の振替口座は引継がれませんので、後期高齢者医療制度の保険料としての口座振替の申し込みが必要です。
納付書払い
指定金融機関の窓口にて、納付書と現金により納めていただきます。コンビニ収納、スマホ決済、クレジットカードには対応しておりませんのでご注意ください。
口座振替申し込み窓口・納付書による納付可能場所(指定金融機関)
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 熊谷商工信用組合
- ふかや農業協同組合
- 埼玉縣信用金庫
- 東和銀行
- 関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
納付書による納付可能場所
- 埼玉りそな銀行寄居町役場内派出所