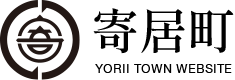本文
国民年金について
国民年金とは
国民年金は、高齢になったときの所得保障だけでなく、重い障害や死亡といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、皆で前もって保険料を出し合い、お互いの生活を支えあう制度です。
【目 次】
1、被保険者
2、加入手続き
3、保険料
4、保険料の免除
5、年金の受給
手続きの内容によっては、年金事務所または役場窓口のほかに電子申請(マイナポータル)で受け付けしています。詳しい内容は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(注)年金事務所または役場窓口で手続きする場合は、それぞれの手続きに必要な書類に加えて「2、加入手続き」に掲載の持ち物(原本)をご用意ください。
被保険者
必ず加入する人(強制加入者)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は必ず加入しなければなりません。日本在住の外国籍の方も対象です。加入者は次の3種類に分かれます。
- 第1号被保険者 【保険料を自分で納付する必要がある方】
自営業や学生など第2号被保険者と第3号被保険者ではない方 - 第2号被保険者 【保険料を給料天引きにより納付する方】
会社員や公務員など厚生年金に加入している方 - 第3号被保険者 【保険料を自分で納付する必要のない方】
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
希望により加入する人(任意加入者)
強制加入の被保険者ではなくなった場合でも任意加入できる場合があります。詳しい内容は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 高齢任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも届け出により国民年金に加入できます。
(注)下記の1~4すべての条件を満たす方が対象です。
1.日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
2.老齢基礎年金を繰上げ受給していない
3.保険料の納付月数(20歳以上60歳未満までの間)が480月(40年)未満である
4.手続き時に、厚生年金保険・共済組合等に加入していない - 海外任意加入
国外に居住すると国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方は届け出により国民年金に加入できます。 - (注)下記の1~5すべての条件を満たす方が対象です。
1.日本国籍である
2.海外に居住する20歳以上65歳未満である
3.老齢基礎年金の繰上げ受給していない
4.(60歳以上の場合)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
5.手続き時に、厚生年金保険・共済組合等に加入していない、またはその被扶養配偶者ではない方
加入手続き
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、国民年金の加入手続きが必要です。また、国民年金第1号被保険者はご自身で保険料を納める必要があります。
加入手続きは、電子申請(マイナポータル)や年金事務所、役場窓口で受け付けしています。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(注)年金事務所または役場窓口で手続きする場合は、それぞれの手続きに必要な書類に加えて以下の持ち物(原本)をご用意ください。
- 本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 - マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)、または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書・年金手帳等)
- 代理人が届出を行う場合は委任状
20歳になったら国民年金
20歳になってから2週間程度で日本年金機構から基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が郵送されます。
(注)基礎年金番号通知書は20歳以前に厚生年金に加入していたり、遺族年金を受給していた方には送付されません。
(注)学生や所得が少なく保険料を納めるのが困難な場合は、納付猶予や免除の制度があります。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>では、20歳になった人の加入や保険料の納付、免除の制度などをわかりやすく動画で案内しています。
保険料
保険料額
国民年金の保険料額は国が決定し、被保険者の所得に関係なく一律の金額です。
納付した保険料は所得税や個人住民税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。
- 定額保険料
国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者は、国民年金保険料の納付が必要です。保険料額(金額は日本年金機ホームページ<外部リンク>をご覧ください)は物価や賃金の伸びに合わせて毎年度見直しを行っています。 - 付加保険料
定額保険料と一緒に納付することで、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せできます。保険料額や手続きについては、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
納付方法
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。また、保険料はまとめて納付したり、納付方法によっては割引があります。
納付方法は以下のとおりです。詳しい内容は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 銀行・郵便局などの金融機関、コンビニエンスストアなどで現金納付
- 口座振替で納付
- クレジットカードで納付
- スマートフォンアプリで納付
- ねんきんネットで納付
保険料の免除
国民年金保険料の納付が経済的に難しいときは、手続きにより負担を減らすことができます。詳しい内容は以下の制度ごとのリンク先(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
- 申請免除<外部リンク>
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。 - 納付猶予<外部リンク>
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 - 学生納付特例<外部リンク>
本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により承認されると学生期間の保険料の納付が猶予されます。 - 法定免除<外部リンク>
生活保護法による生活扶助を受けている・障害年金(2級以上)を受給している場合など、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。 - 産前産後期間免除<外部リンク>
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合は、届出により出産前後一定期間の保険料が免除されます。
年金の受給
国民年金には、65歳になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、加入中に亡くなったときに受給できる年金などがあります。金額や手続きは以下の制度ごとのリンク先(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
- 老齢基礎年金<外部リンク>(65歳になったとき)
- 障害基礎年金<外部リンク>(加入中のケガや病気で障害が残ったとき)
- 遺族基礎年金<外部リンク>(配偶者・子どもを残して亡くなったとき)
- 寡婦年金<外部リンク>(老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受給する前に亡くなったとき)
- 死亡一時金<外部リンク>(保険料を3年以上納付した方が年金を受給する前に亡くなったとき)
- 特別障害給付金<外部リンク>(任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給していないとき)
- 脱退一時金<外部リンク>(保険料を6か月以上納付した外国籍の方が年金を受給する前に出国したとき)
- 年金生活者支援給付金<外部リンク>(年金受給者の公的年金等の収入やその他の所得が一定額以下のとき)