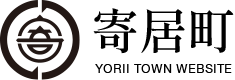本文
出産育児一時金について
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる場合は48万8,000円)が支給されます。
また、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金直接支払制度とは、世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち50万円(産科医療補償制度の対象外となる場合は48万8,000円)についてはお支払いが不要になります。
直接支払制度を利用する場合
制度利用については、出産予定の分娩機関に直接お問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円(産科医療補償制度の対象外となる場合は48万8,000円))を下回った場合、町へ申請することで差額分が支給されます。差額支給の申請に必要なものは以下のとおりです。
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産された方のマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
- 分娩機関と結んだ、直接支払制度を利用する旨の合意文書等
- 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収書、明細書等)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
直接支払制度を利用しない場合
分娩機関の窓口で出産費用を全額支払い、町へ出産育児一時金の申請をしてください。申請に必要なものは下記のとおりです。
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産された方のマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
- 分娩機関と結んだ、直接支払制度を利用しない旨の合意文書等
- 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収書、明細書等)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
出産育児一時金受取代理制度
出産育児一時金受取代理制度とは、分娩機関で申請書を作成後、町へ申請することで、出産育児一時金の受取について分娩機関に委任するという制度です。国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支給するため、出産費用のうち50万円(産科医療補償制度の対象外となる場合は48万8,000円)についてはお支払いが不要になります。
受取代理制度を利用する場合
制度利用については、出産予定の分娩機関に直接お問い合わせください。申請に必要なものは下記のとおりです。なお、申請書については、町民課窓口にてお渡しします。
- 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
- 出産された方のマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード