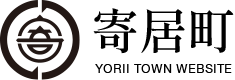本文
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
令和6年度に国の物価高騰対策として「定額減税」及び「定額減税補足給付(調整給付)」(以下、「当初調整給付」)が行われました。その追加措置として、確定申告や年末調整等で令和6年分所得税額及び定額減税額の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
「定額減税」の詳細については、内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の詳細」<外部リンク>をご確認ください。
「当初調整給付」の詳細については、町公式ホームページ「定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。
※以下の掲載内容は令和7年7月3日時点の情報であり、今後内容が随時変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
給付対象者
令和7年1月1日時点で寄居町に住民登録があり、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
ただし、本人(納税義務者)の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
令和6年分所得税額及び定額減税額の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額などに差額が生じた方
給付額
「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との差額を1万円単位に切り上げて支給(支給額は対象者ごとに異なります)
給付対象となりうる方の例
○令和5年中の所得税額より令和6年中の所得税額が減少した方(退職、育休等)
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
(例1)納税者本人・配偶者・子ども1人の3人世帯の場合
※所得税分の定額減税可能額 = 3人(本人+配偶者+子ども1人)×3万円
※個人住民税所得割は変動なし
令和5年所得 60,000(推計所得税額)- 90,000(所得税分の定額減税可能額)
= 30,000(当初調整給付額)… (1)
令和6年所得 45,000(実績所得税額)- 90,000(所得税分の定額減税可能額)
= 45,000(本来給付すべき額)… (2)
(2) - (1) = 15,000
「(1)当初調整給付額」と「(2)本来給付すべき額」の差額15,000円を1万円単位で切り上げ、20,000円を不足額給付金として支給
○令和6年中に出生等で扶養親族が増えた方
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
(例2)納税者本人・配偶者の2人世帯だったが、令和6年中に子どもが生まれ、3人世帯となった場合
※所得税分の定額減税可能額 (a) = 2人(本人+配偶者)×3万円
↓
※所得税分の定額減税可能額 (b) = 3人(本人+配偶者+子ども1人)×3万円
※個人住民税所得割は変動なし
当初調整給付時 30,000(推計所得税額)- 60,000(所得税分の定額減税可能額(a))
= 30,000(当初調整給付額)… (1)
不足額給付時 30,000(実績所得税額)- 90,000(所得税分の定額減税可能額(b))
= 60,000(本来給付すべき額)… (2)
(2) - (1) = 30,000
「(1)当初調整給付額」と「(2)本来給付すべき額」の差額30,000円を不足額給付金として支給
※端数は1万円単位で切り上げ
○当初調整給付後、修正申告により令和6年度の住民税所得割が減少した方
不足額給付2
本人および扶養親族などとして定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付金対象世帯の世帯主と世帯員にも該当しなかった方
給付額
次の(1)から(3)すべての要件を満たす方に、原則4万円(定額)
ただし令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
(1) 本人として定額減税対象外
(令和6年所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円)
(2) 税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族としても定額減税対象外)
(3) 低所得世帯向け給付金(※)の世帯に該当していない
※低所得世帯向け給付金とは以下のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる方の例
○事業専従者の方
○合計所得金額が48万円を超える方
「事業専従者」の詳細については、国税庁ホームページ「青色事業専従者給与と事業専従者控除」<外部リンク>をご確認ください。
実施方法
支給対象となる方には、8月上旬から順次通知を発送いたします。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)※必着、消印有効
※期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんのでご注意ください。
本給付金を装った詐欺等にご注意ください
寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
町の職員をかたった不審な電話や郵便などがあった場合は、直ちに最寄の警察署へご連絡ください。
※給付金の対象者に関する個別のお問い合わせには、電話やEメールではお答えできません。